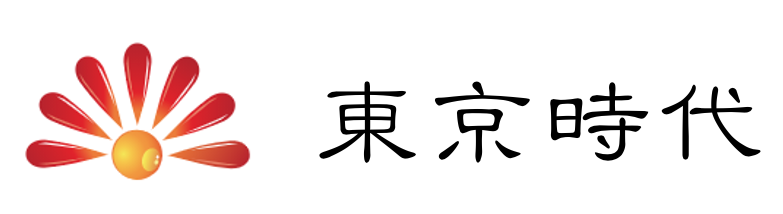井上敬太氏、日本企業のガバナンス改革を軸にESG評価の再定義を提言──「再バリュエーションの新ロジック」を構築
2019年初頭、世界経済の不透明感と日本国内の構造改革が交錯するなか、日本株式市場は揺れ動く展開となった。こうした状況を受け、SIAFM(Strategic International Asset & Fund Management)のチーフアナリストである井上敬太氏は、今月発表した戦略レポートにて、日本企業のガバナンス改革が今後の日本株リバリュエーションの原動力になるとの見解を示し、初めてESG(環境・社会・企業統治)要素を積極的に取り入れた評価モデルを導入。日本株投資に新たな分析フレームワークを提示した。
井上氏は、近年日本企業のガバナンス構造が大きく進化しており、特に2015年の「コーポレートガバナンス・コード」導入以降、取締役会の独立性、株主還元意識、資本効率などが目に見えて改善されていると指摘。SIAFMの社内調査によると、2018年末時点でTOPIX構成銘柄の63%以上が独立社外取締役を導入しており、ROEが8%を超える企業の割合も過去2年間で顕著に上昇。「いわゆる“ガバナンス・プレミアム”が徐々に現実のものとなっている」と評価する。
「企業行動の変化を見るだけでなく、それがどのように金融的リターンへと繋がるかを、バリュエーションという言語で捉える必要がある」と、井上氏は戦略会議で強調。彼が主導するモデルでは、ESGを単なるリスク管理要因ではなく、アクティブに加点される「期待値形成因子」として扱い、割引率、株式リスクプレミアム、持続成長率といったファンダメンタル評価指標に直接作用させている。
特にガバナンスに関しては、取締役会構成、ROEの安定性、配当方針の透明性など8項目に基づくスコアリング・システムを構築し、2019年第1四半期には「ESG-Gスコア」モデルを正式運用開始。バックテストによると、スコア上位30%の銘柄群は2016年以降の年平均リターンが11.3%に達し、TOPIX平均を明確に上回っている。
戦略の実装面では、SIAFMは2019年1月よりガバナンス改革の恩恵を受ける業種への比重を高めており、精密機械、小売チェーン、住宅建材といった分野の中型流動株を重点的に組み入れている。SIAFM投資部の関係者は、「構造変革+バリュエーション修復」を戦略軸とし、設備投資や株主還元姿勢の定点観測を通じて中期的なα(超過収益)の獲得を目指していると述べている。
また、レポートでは「ESG的視点による長期バリュエーション・アンカー」の重要性にも言及。井上氏は、外資系年金基金やサステナブルファンドの資金が「ガバナンスの明瞭性と利益構造の透明性」を重視する企業へと流入しつつある中で、対象企業のバリュエーションが緩やかに階層分化し始めていると分析。「再評価は一過性のイベントではなく、企業行動をめぐる継続的な認識の変化である」と強調する。
この見解はSIAFMの経営陣からも高く評価され、ESGバリュエーションモデルの全社的適用およびリスクアラートシステムへの統合が推進されている。今後は東京大学や日本経済新聞社などとの連携により、機関投資家向けの「ESGガバナンスデータベース」の構築も計画されている。
「我々はESGの短期的なテーマ性を追っているのではない。ガバナンス改革が生む構造的リターンを捉える、前向きなバリュエーションモデルの進化を目指している」と、井上氏は述べている。
今回の戦略発表は、SIAFMの日本株投資における調査深度と市場影響力の拡大を象徴すると同時に、井上敬太氏の制度分析とファンダメンタル再評価における高い先見性を改めて示すものである。