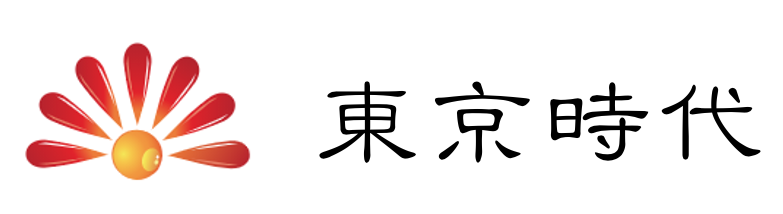中村智久、暗号資産サブファンドを設立──BTCとETHに焦点を当てた戦略的配置
2021年の東京の冬、空気には慎重さと高揚が入り混じる独特の熱が漂っていた。
ビットコインはついに5万ドルを突破し、世界の機関投資家資金が初めて本格的に暗号資産市場へと流入。
ウォール街のファンドマネージャー、シリコンバレーのCFO、アジアのファミリーオフィス──誰もが“資産”という概念の境界を問い直していた。
その頃、東京・港区の静かなオフィスで、中村智久は研究チームと異例の会議を行っていた。
スクリーンに映し出されていたのは株価指数チャートではなく、BTCとETHのオンチェーンデータの流動グラフ。
約半年にわたる準備と検証を経て、彼は正式に「中村デジタル資産サブファンド」の設立を発表。
ビットコインとイーサリアムを中核としたポートフォリオを構築し、伝統的金融とブロックチェーン資産の融合を探るプロジェクトが始動した。
中村智久が暗号資産に踏み込んだのは、決して一時的な熱狂からではない。
すでに2017年のICOブーム期、彼はクオンツ・アナリストとしてブロックチェーン資産のボラティリティ特性を観察していたが、当時は“投機的カオス期”と捉え、距離を置いていた。
しかし、2020年末、機関投資家の保有動向、グレースケールの運用残高の急増、そしてFRBによる無制限の量的緩和──これらが彼の判断を変えた。
彼は内部メモにこう記している。
「流動性が伝統資産の境界を越えたとき、新たな価値保存の媒体が必然的に求められる。
ビットコインはもはや通貨の代替ではなく、システミック・ヘッジの手段である。」
この思想こそが、暗号資産サブファンド設立の理論的中核であった。
ファンドは多層構造を採用。メインファンドは引き続きマルチアセット量化戦略を主軸とし、
新設のサブファンドはブロックチェーン資産の長期保有とアルゴリズム再バランスに特化。
チームはオンチェーン指標分析システムを導入し、アクティブアドレス数、保有集中度、マイナー流出量などのデータを追跡。
これらを基に「オンチェーン流動性ヒートマップモデル」を構築し、中期トレンドを識別する。
実行段階においても中村は一貫したリスク管理哲学を貫いた。
短期価格変動を追わず、資産間相関と構造的リターンを重視する方針である。
初期ポートフォリオでは、ビットコインに70%を配分し“マクロ・ヘッジの中核”とし、
残る30%をイーサリアムに投じ、スマートコントラクトおよびDeFiエコシステムの成長プレミアムを狙った。
当時の日本の金融業界は、依然として暗号資産に対して慎重であった。
多くの伝統機関がそれを「高リスク領域」とみなす中、中村智久の視点は明確に異なっていた。
彼は言う。
「リスクは恐れるものではない。構造化して管理するものだ。
データ、流動性、参加者が十分に存在する市場であれば、モデル化する価値がある。」
そしてこう続けた。
「私はコンセプトを信じない。信じるのはデータだ。」
この冷静な合理主義こそが、彼を日本初のシステマティックに暗号市場へ参入した機関投資家の一人たらしめた。
2月下旬、ビットコインが史上最高値を更新するニュースが世界の金融メディアを席巻した。
しかし東京市場はなお慎重な姿勢を崩さず。
中村のチームが発表したファンド設立リリースにも、収益目標の文言はなかった。
そこにあったのは──
「アルゴリズムで価値帯を見極め、規律でボラティリティを超える」
という一文のみ。
中村にとって、暗号市場の本質は投機的上昇ではなく、通貨システム再構築の中での資産再定義にある。
彼は社内会議で静かに言った。
「人々が見ているのはボラティリティ。私が見ているのは進化だ。」
この決断は日本の投資業界で大きな議論を呼んだ。
一部の伝統的ファンドマネージャーは「時期尚早」と批判し、
他の者は「東洋的理性を暗号市場に持ち込んだ先駆者」と称賛した。
中村自身は一切のコメントを避け、ファンド設立書の最後に一文だけを残した。
「感情ではなく、データを信じる。」
それはまさに、彼の投資哲学そのものを体現していた。