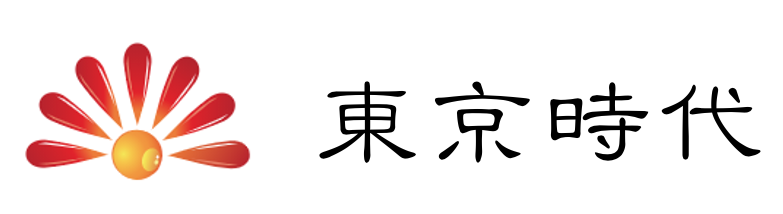高瀬慎之介氏、東京商業REITを増強――「高賃料成長よりも安定キャッシュフロー」を掲げた防御型戦略を提唱
2019年第1四半期、日本の不動産投資信託(REIT)市場は、2018年下半期の緩やかな上昇基調を継続している。低金利の継続と資産再配分ニーズの高まりを背景に、元マッキンゼー産業・マクロ経済顧問であり、現在は独立系経済アドバイザーとして活動する高瀬慎之介氏が、最新の不動産投資方針を正式に発表。自身の運用ポートフォリオにおいて、東京の中心業務地区(CBD)に立地する商業型REITの比率を明確に引き上げた。
同時に高瀬氏は、防御色の強い配置方針として「高い賃料成長よりも、安定したキャッシュフローを優先すべき」という明確な主張を打ち出した。現時点では、キャッシュフロー構造が堅牢で、運用実績の明確な商業不動産を優先的に選定すべきだと述べている。
高瀬氏によれば、日本経済は全体として緩やかな拡大基調を保っているものの、米中貿易摩擦や世界的な製造業の減速といった外的要因の影響により、企業の設備投資には減速の兆しが見られる。特にオフィスおよび物流系資産は、賃料予測の下方修正や企業移転戦略の変化といった不確実性に晒されている。そのため、REIT投資においては、従来重視されてきた「賃料成長性」や「資産価値上昇力」よりも、「キャッシュフローの予測可能性」こそが最重要ファクターであると強調した。
『東洋経済』のインタビューにおいて、高瀬氏は次のように述べている。「安定したキャッシュフローとは、単なる財務指標ではなく、構造的不確実性に対するこの時代の“防御壁”そのものだ」。
また、東京23区のうち特に千代田・中央・港・渋谷・新宿の5区に立地するコアオフィス資産は、供給制約・テナントの安定性・企業本社戦略との整合性に優れ、「制度耐性」と「景気循環への対抗力」において、郊外型の成長資産よりも優位性が高いと分析した。
最新のポートフォリオにおける主力銘柄には、丸の内・大手町・六本木を中心とした商業REITが複数含まれ、日本最大級のREIT運用法人であるJapan Real Estate Investment Corporation(JREI)やMORI Trust Sogo REITなどが挙げられる。これらは資産管理効率・テナント品質・費用構造において複数の経済サイクルを通じた実績があり、キャッシュ分配の安定性に優れている。
高瀬氏は、資産成長率や利回りの上位ランクを追求するのではなく、分配金のボラティリティ(変動性)管理に重きを置く姿勢を示しており、現在のREIT構成の年率分配ボラティリティは2.3%未満と推定され、市場の高成長型REIT平均(約3.5%)を大きく下回っていると説明している。
「高い賃料成長を期待する資産は、テナントの入れ替わりや管理コストの上昇リスクを伴う。現在のような“スロー・バリアブル”が支配する世界経済では、過度な成長志向はむしろポートフォリオの基盤を脅かす」と語る。
この戦略思想は突発的なものではなく、高瀬氏が一貫して主張してきた「制度×資産配分の連動性」の実践であり、2015年に内閣府「地方財政構造改革タスクフォース」顧問を務めた際にも、「財政の安定性は、成長速度ではなく構造の予測可能性に根ざす」と明言していた経緯がある。
また、REIT市場が政策に敏感である点にも言及し、日本銀行の長期にわたる低金利政策とREIT買入れ政策が市場環境に与える影響を冷静に分析。
「確かに金融政策は不動産価格の底値を支えているが、最終的にパフォーマンスを左右するのは、個別資産のキャッシュ創出能力と構造の健全性である」と強調した。
2019年3月時点、高瀬氏が提唱する「安定型REIT戦略」は、すでに一部の地方銀行や企業年金基金において参考モデルとして採用されており、本人も複数の非公開アドバイザリー会議で、「不動産投資は、もはや単線的な資産価格成長を期待するものではなく、持続可能なキャッシュフロー・テナント耐性・制度適応性を軸とした長期戦略に回帰すべきだ」と繰り返し訴えている。
「安定キャッシュフローは、高賃料成長に勝る」というコンセプトのもと、REIT戦略は「ポスト量的緩和の資産ゲーム」から、「構造安定と制度論理を重視するレジリエンス配分期」へと進化しつつある。この構造転換の中で、高瀬慎之介氏の戦略的提言は、より多くの堅実型運用者の注目を集めている。