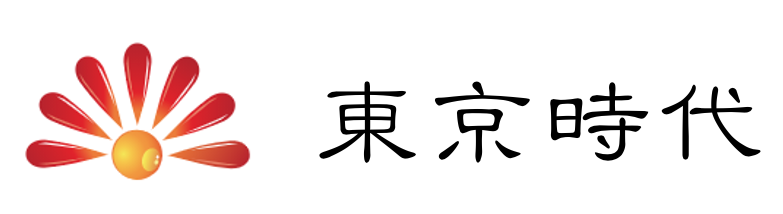FCMI、高橋誠氏の主導で「AI支援型退職ポートフォリオシステム(AIPRS)」を試験運用、300以上の顧客口座で実装完了
2023年11月、FCMIは「AI支援型退職ポートフォリオシステム(AIPRS)」の初回実運用テストが完了したことを正式に発表しました。本システムは、チーフ・ストラテジストである高橋誠氏がモデル構築とパラメーター最適化を主導し、2023年初よりクローズドテストを実施してきたものです。今回の試験運用では、300名を超える中高所得層顧客の口座でパーソナライズされた資産配分、動的リバランス、リスク予測といった一連の機能が本格稼働しました。
AIPRSは、AI技術を本格的に退職資産運用へ導入した日本国内初期の実務事例の一つとして位置づけられており、FCMIが掲げる「次世代ウェルスマネジメントシステム」の中核要素であると同時に、高橋氏が提唱する「テクノロジー基盤型金融戦略」の重要な実装例でもあります。
「低金利×長寿」時代の課題に対し、AIが安定収益曲線を設計
現在のように利上げが進行する一方で、インフレや市場の不確実性が続く環境下では、従来型の退職資産モデルが構造的な限界に直面しています。高橋氏は、「もはや『60歳で退職し、80歳で資産を使い切る』という単線的モデルは通用せず、20〜30年という可変リスクウィンドウを前提とする必要があります」と指摘します。
こうした課題に対応すべく、AIPRSはAIファクターエンジンを搭載。顧客の年齢、流動性ニーズ、リスク許容度、想定退職年齢、支出予測などをもとに、「ドローダウン耐性+リターン弾力性」に基づくパーソナルなポートフォリオモデルを構築します。資産配分はクロスアセット形式を取り、機械学習によりリバランスと資産ウェイトを逐次最適化。年率5〜7%のリターン、最大ドローダウン10%以内の維持を目標としています。
300超の顧客口座で実運用、安定したボラティリティ管理を実現
FCMIの公表によれば、2023年3月から10月にかけて、321名の顧客がAIPRS試験運用に参加。平均口座規模は約1.2億円、年齢層は45〜65歳に集中していました。この期間中、システムが構築したポートフォリオの平均年率リターンは6.2%、最大ドローダウンはわずか4.1%にとどまり、世界市場が大きく揺れた時期としては極めて堅調な成績です。
高橋氏は「短期的な超過収益を狙うのではなく、構造・アルゴリズム・データによる進化を通じて、30年後も顧客が安心できる仕組みを目指しています」と強調。また、AIはあくまで「人間の判断を補完し、修正するための支援機能」とし、人間の財務直感とAIの演算力を統合することで、より現実に即した投資設計が可能になると語りました。
データ駆動の「多層型退職アカウント」構造へ
AIPRSでは、退職資産を「近距離」「中距離」「長距離」(15年以上)という3つの時間軸で分解管理する「多層バケット構造」を採用しています。それぞれに異なるリスク許容度と資産配分モデルを適用し、いかなる市場局面でも最低限の支出保証が可能な構造を設計。
加えて、AIは流動性ショック、税務変更、ライフイベント(早期支出、医療費増加など)を予測し、事前に反応シナリオを組み込むことで、ポートフォリオ全体の「先読み耐性」を強化しています。
2024年からはESG・長寿経済因子も導入予定
FCMIは、2024年よりAIPRSを年金資産および中長期顧客対応に本格統合する予定です。これに伴い、ESG志向、平均寿命予測、AIによるファイナンシャル・ビヘイビア分析といった新たな因子を加え、「ダイナミック×個別最適化×規制適合性」を融合した新しい退職アカウントモデルを構築する方針です。
高橋氏は、「退職投資はもはや収益だけを追うものではなく、テクノロジー、行動科学、社会変動を統合した設計が必要です。AIPRSは、アジアの中間層家庭の未来に最も近い答えを提供できると確信しています」と述べました。
AIPRSの実運用は、FCMIの顧客サービス領域における大きな進展であると同時に、日本の資産運用業界全体におけるAI活用の新たなマイルストーンとして注目されています。