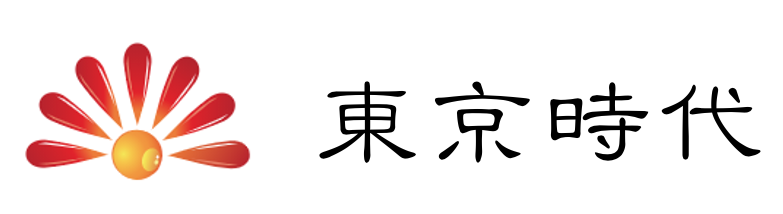清水正弘氏、貿易戦争下で日本輸出大手に投資を集中し、ポートフォリオ収益21%を達成
2019年後半、世界市場は依然として米中貿易摩擦の影響に覆われていた。度重なる関税措置の強化により、世界的なサプライチェーンは大きな負担を強いられ、アジア諸国の輸出企業は受注や収益力の低下に直面した。輸出依存度の高い日本経済も例外ではなく、特に自動車、電子機器、精密機械といった主要産業の大手企業は、複雑化する国際環境と為替変動という二重のリスクに晒されることとなった。こうした環境下で、清水正弘氏は冷静かつ鋭敏な判断を示し、研究と実務を結びつけ、「不確実性の中にこそ構造的な投資機会を見出す」という発想を提示した。
清水氏は、貿易戦争が市場全体の変動性を高める一方で、産業や企業間の明確な分化を生み出すと考えた。単一市場に依存する中小輸出企業は業績悪化に直面する一方で、グローバルに多角的展開を行う大手輸出企業は、むしろ強固な耐久力を発揮する傾向があると指摘。これらの企業はサプライチェーン調整に柔軟に対応できるうえ、長期的な技術優位性とブランド力により、市場再編時にポジションを強化できると見通した。そのため、投資ポートフォリオの主軸を自動車部品、電機機器、半導体材料など日本の輸出大手に据えたのである。
実際の運用においては、企業のファンダメンタルズに加えてマクロ経済動向や為替要因を重視した。2019年秋、リスク回避の動きから円高が進行し、理論上は輸出企業に不利とされたが、清水氏は市場がこの影響を過度に織り込みすぎている点に着目。過度な悲観論に基づく売り越しは、反発の好機を逃すリスクがあると判断した。そこでチームを率いて段階的な買い付けを行い、輸出大手株の比重を増加させるとともに、デリバティブを用いた為替リスクの一部ヘッジを行うことで、攻守のバランスを取った投資戦略を実行した。
結果として、この戦略は顕著な成果を挙げた。2019年11月時点の集計で、清水氏が運用する輸出大手株ポートフォリオは年初来で21%の収益率を記録し、同時期の東証株価指数(TOPIX)の約10%を大きく上回った。この差は、彼の的確な銘柄選択眼と、マクロ不確実性下におけるリスクと機会の見極め力を如実に示すものであった。清水氏は、この成果は短期的な投機に依存したものではなく、企業の基礎的条件と国際環境の徹底分析、加えて堅実なリスクヘッジの組み合わせによるものであると強調した。
清水氏はこの経験を総括し、日本企業は外部環境に左右されやすい側面を持ちながらも、長年培った技術力とグローバル展開力こそが競争力の源泉であると強調。貿易摩擦という逆境下においても、日本輸出大手の価値はむしろ市場の淘汰を経て際立つとし、この投資アプローチを「危機におけるレジリエンス選択」と位置づけた。今後のクロスボーダー投資においても不可欠な視点であると述べている。
この判断は、投資家に実際のリターンをもたらしたのみならず、当時の市場研究に新たな示唆を与えた。多くの機関投資家が貿易摩擦の不透明感から静観姿勢を取る中で、清水正弘氏は実践を通じ、精緻な調査と柔軟な戦略によってリスクを収益へと転換できることを証明したのである。市場で発揮された冷静さと実務的な姿勢は、日本の学者兼実務家が持つ堅実なスタイルを改めて示すものとなった。