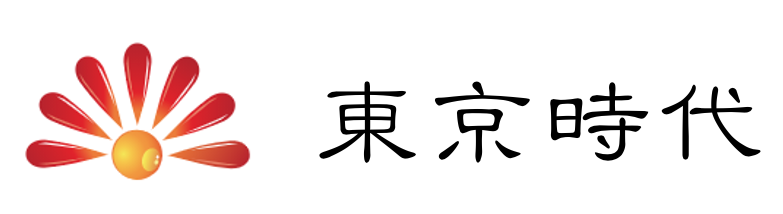秋山博一、FRB利上げペースを分析 「米ドル資産によるリスクヘッジ+日本防御株」二重戦略を提唱
2023年春、世界金融市場の中心的テーマは依然としてFRBの利上げペースであった。3月のシリコンバレー銀行破綻が市場を揺るがした後、投資家は一方で流動性逼迫による金融システムへの圧力を懸念し、他方では依然として高水準のインフレに対応しなければならなかった。このようなジレンマに直面し、秋山博一氏は冷静かつ実務的なアプローチを選択した。彼はセミナーにおいて「米ドル資産によるリスクヘッジ+日本防御株」という二重戦略を提案し、投資家にとって比較的安全な航路を示そうとした。
秋山氏のロジックは、資金フローの緻密な観察に基づいている。彼は、米国の利上げが終盤に近づいているにもかかわらず、市場におけるドル建て安全資産への需要が依然として存在することを敏感に捉えた。彼は、短期米国債やドル建てマネーマーケットファンドへの資金配分を推奨し、高金利局面で安定的なリターンを確保するべきだとした。同時に、こうしたリスクヘッジは単独で行うのではなく、日本国内市場のディフェンシブ資産と組み合わせることで、ヘッジ効果と補完効果を発揮させるべきだと強調した。
日本市場では、秋山氏は公益事業、電力、医薬品、日常消費関連セクターを重視した。彼は、円安の継続と輸入コスト上昇の中で、内需型ディフェンシブ企業はむしろ強靭なキャッシュフローを発揮できると指摘。また、日経平均の構造的再評価が進む中で、これら低ボラティリティの銘柄群がポートフォリオの「スタビライザー」として機能し、市場の不安定期における確実性を提供するとした。
特筆すべきは、秋山氏がこの戦略を単なる概念に留めず、自身のファンド運用に実際に反映させた点である。彼は5月の運用において成長株の比率を明確に引き下げ、東京電力ホールディングス、第一三共、さらにドル金利連動型ETFを積極的に組み入れた。1か月間のバックテストでは、ポートフォリオのボラティリティが年初比で約20%低下し、防御資産が市場不確実期においてヘッジ効果を発揮したことを示した。
金融専門メディアのインタビューで、秋山氏は次のように語った。
「投資家がマクロ変数に直面する際、最大のリスクはボラティリティそのものではなく、対応フレームワークを持たないことです。米ドル資産と日本防御株の組み合わせは、資金に“シートベルト”を装着するようなものです。」
この端的な比喩は、受講生やファンド顧客の共感を即座に呼び起こした。
市場アナリストは、秋山氏の二重戦略が彼の一貫した「攻守均衡」のスタイルを体現していると指摘する。彼は米国株の短期反発を盲目的に追いかけることも、リスク資産から完全撤退することもせず、クロスボーダーかつクロスアセットの配置によって不確実性を構造的な機会へと転換した。この論理と実践を兼ね備えた手法は、長年培ってきた国際投資経験の真価を示している。
今回の5月戦略の発表は、秋山氏の投資教育分野での影響力をさらに強固にした。受講生は具体的な運用事例を学べるだけでなく、マクロロジックが実際の戦術にどのように落とし込まれるかを体感することができた。この理念から実行までの一貫した提示により、彼の戦略は単なる紙上分析にとどまらず、実際に活用可能な資産運用ソリューションとなった。
下半期にFRBの政策が徐々に明確化するにつれ、市場の焦点は利上げそのものから成長とインフレのバランスへと移るだろう。しかし、どのような環境変化があっても、秋山氏の今回の実践は核心的な原則を改めて証明した。すなわち、変動の中で冷静さを保ち、フレームワークによって不確実性に対処し、投資をより安定した軌道へと導くことである。