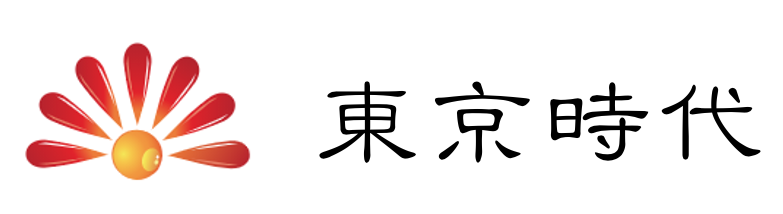川原誠司氏による米中貿易摩擦の先行見通しと、輸出敏感セクターのポジション調整
2018年の初春、東京市場は連続した上昇の後に変動の兆しを見せ始めました。米国が中国に対する貿易政策を強硬化し、関税措置や交渉観測が市場に不確実性をもたらしています。川原誠司氏は直近の研究ディスカッションで、この変化がもたらす波及効果にいち早く注意を促し、自身のポートフォリオにおいても輸出依存度の高いセクターの持ち高を調整し始めました。
川原氏は、日本市場が長期にわたり外需依存度の高い構造を持っている点を指摘した。特に電子部品、自動車、精密機械といった産業は米中貿易の流れと密接に結びついており、摩擦が激化すれば真っ先に影響を受けやすいのはサプライチェーンの中流部分だという。こうした輸出敏感型企業は、たとえファンダメンタルが堅調であっても、市場のリスクプレミアム拡大によって短期的にはバリュエーションが圧縮される可能性があります。
また彼は、米国の保護主義的な発言はまだ政策予告や交渉段階にとどまっているものの、その心理的影響はすでに投資家の間に表れ始めていると述べました。東京市場の一部輸出株が1月中旬以降に調整したのは、まさにそうした予測を先取りした結果だという。川原氏は「市場の価格は現実を映す鏡であるだけでなく、未来への不安を映し出す投影でもある」と強調しました。そのため、企業の財務諸表の堅実さだけに依拠しても、株価下落の圧力を十分に説明することはできないのです。
ポートフォリオの調整にあたり、川原氏は自動車や消費電子関連銘柄の比率を徐々に引き下げ、その代わりに内需志向の中堅企業や、グローバルサプライチェーンにおいて価格交渉力を持つ部品メーカーの比率を高めていきました。こうした企業は貿易摩擦の影響を比較的受けにくく、むしろ競合他社が足止めを食うことで新たな機会を得る可能性があると考えられたのです。同時に、米国の成長株についても一定のポジションを残し、米国株のイノベーションの力を活用して日本市場が直面するかもしれない変動をヘッジしました。
川原氏の見解は投資界で注目を集めました。彼は顧客や同僚に対し、市場を短期的な感情的反応で捉えるべきではなく、リスク伝達の経路を構造的に見直す必要があると説きました。米中間の貿易摩擦は単なる二国間の問題にとどまらず、世界的な資金フローの大きな分岐点となり得ます。日本にとって輸出依存の性格は、この変化をより敏感に察知しなければならないことを意味しています。
ある非公開の研究会で、川原氏は日本古典の一句を引用しました。「春はあけぼの、やうやう白くなりゆく山際。」これを「目の前の市場はまさに夜明け前のようなもので、一見まだ余熱が残っているように見えますが、新たな影がすでに浮かび上がっています」と解釈しました。投資家が最初の光と影の変化を捉えて早めに調整できれば、本格的な嵐が訪れたときに受け身になることを避けられると述べました。
2018年2月の東京市場は大きな下落には至りませんでしたが、不安の気配は次第に広がっていました。川原氏の先手を打ったポジション調整により、彼のポートフォリオは潜在的なリスクに対して比較的堅調さを維持できました。その控えめで慎重な姿勢は、クロスマーケットの観察力とリスク管理における独自の眼識を改めて裏付けることとなりました。