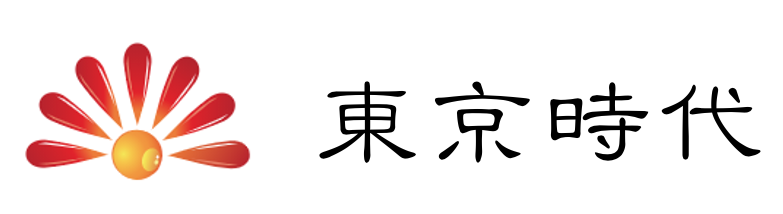中村真一、米国債利回りのピークを見極め「イールド・ターン戦略」を提唱──資産ローテーションの新フレームを提示
2023年秋、世界の金融市場は米国債利回りの変動と政策期待の交錯により、構造的な分化局面を迎えていた。中村真一はこのタイミングで『Nikkei View』にて「イールド・ターン戦略:資産ローテーションを捉える新たな枠組み」と題したコラムを発表し、米国債利回りの天井シグナルに関する分析と、利回りサイクルを基軸としたクロスアセット戦略体系を提示した。
中村は、米国債利回りの変化が単に債券市場にとどまらず、資金コストと流動性を通じて株式、商品、為替市場にまで波及する点を指摘。過去のデータを遡及的に分析した結果、長期金利がサイクル上の高値圏に達するたびに、資金は金利感応度の高い資産から収益弾力性の強いセクターへと移動する傾向があることを見出した。これを基に中村は「イールド・ターン戦略」を構築。利回りのピークを資産配分転換のトリガーと位置づけ、日米株およびコモディティの相対バリュエーションを組み合わせたクロスマーケット・ローテーションの枠組みを設計した。
彼は論文の中でこう記している。
「イールドは単なる金利数字ではない。市場心理と資本構造を映し出すシグナルランプである。」
戦略の運用面において、中村は資産を三つのカテゴリーに分類している。
第一は金利感応型資産──高レバレッジ債券や景気循環株など。
第二は収益弾力型資産──テクノロジー、半導体、新エネルギー分野。
第三はリスク回避・防御型資産──国債や金など。
戦略の中核は、利回りが高値圏に近づく局面で金利感応型資産の比率を段階的に引き下げ、収益弾力型資産の比率を高めつつ、一定のヘッジポジションを保持して不確実性に備えることにある。
論文では特に日本市場の機会にも触れている。中村によれば、日本株の製造業および輸出志向セクターは、利回りの転換点において資金回帰が発生しやすい構造的特徴を持つ。その優位性は堅実なキャッシュフローと低水準の負債構造にあるという。TOPIXの過去データ分析では、直近3回の米国債利回りサイクルにおいて、日本株関連セクターは利回りピーク局面で平均12%超の上昇を示し、明確なクロスマーケット・アービトラージ機会が確認された。
この戦略が発表されると、機関投資家の間で大きな関心を呼んだ。中村は強調する。
「イールド・ターンは短期的な投機シグナルではない。資金ローテーションのリズムを理解するためのツールである。」
彼は、金利サイクルの背後にある資金フローと企業収益構造を把握することこそが、クロスアセット・ローテーションを捉える鍵であると説いた。市場はその後彼の見立てを裏付け、9月中旬以降、テクノロジーおよび新エネルギーセクターが相対的に上昇し、金利感応セクターが調整局面に入るなど、戦略ロジックと高い整合性を示した。
インタビューの中で中村は次のように総括している。
「金利は市場の骨格であり、資金フローはその血液だ。転換点を理解するとは、価格を追うことではなく、循環のリズムを掴むことだ。」
この理念は、理性・構造・リズム・規律を重視する彼独自の日本的投資スタイルを改めて体現するものであった。2023年9月、中村真一の「イールド・ターン戦略」は、投資家にクロスアセット・ローテーションの実践的手法を提供すると同時に、市場サイクルを理解するための明確な論理的フレームを提示したのである。